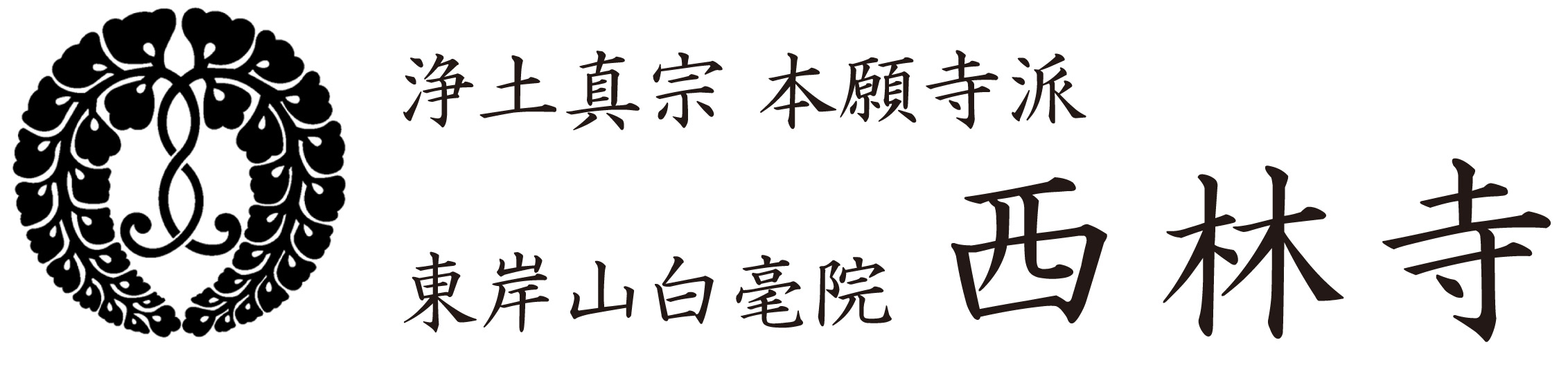何気なく使っている言葉をじっくり眺めてみるといろいろな気づきをいただきます。例えば「命日」という言葉。なぜ、亡くなった人の死亡日を「命日」と言うのでしょうか。「忌日」という用例もありますが、「命日」の方がよく使われます。生まれた日を「命の日」と言うのならわかりますが、亡くなった日を「命の日」と名づけたのは、私たちの先人の深い願いが込められてあるように思います。「命の日」とは、亡き人から私たちに向けられた願いであり、「どうか、私の命日をあなた自身があなた自身の〔命〕と向き合う〔日〕としてください」という願いがこめられた言葉です。ここに命日に仏事を勤め、「私がご縁に遇わせていただく」ことが大切にされてきた意味があります。
また、「亡き人を弔(とむら)う」という表現を耳にしますが、「弔う」は〔とぶらう〕が変化したもので、「訪」という漢字も用います。親鸞聖人は主著の巻末に「前に生れんものは後を導き、後に生れんひとは前を訪(とぶら)へ」とお示しくださいました。
「弔う」とは「訪ねる」ことです。亡き人を訪ねるとは、亡き人から私に向けられたであろう願いを訪ねることです。法事を勤める肝要は、私が亡き人から願われた存在であることの再確認であり、「私のいのちが本当の幸せを恵まれる方向に歩みが進んでゆくこと」だということを仏法をご縁に気づかせていただくのであり、そしてそのことを仏法に問い訪ねてゆくのです。
法事を勤め終えると、「これでひと安心。亡くなった人も喜んでくれているだろう」と達成感に満たされる方もいらっしゃいます。しかし「安心するのはまだ早いぞ。あなたのいのちの行く末は明らかになっていますか。」と亡き人から問いかけられているかも知れません。いただいたご恩のほんの一握り程度しか気づき得ないばかりか、このいのちを支え、育み続けていただいたご恩に、あらためて思いを巡らすこともおろそかに生きている私に、出遇わせていただいたという「存在の事実」は仏さまとなって、今も寄り添い、はたらきかけてくださっているのです。命日をご縁として、あわただしく過ぎ去る日常を立ち止まり、仏さまの教えに耳を傾けたいものです。